日本で最初のフェラチオの記述
- [2009/09/07 00:26]
昨日、母性と吸茎のことを考えていたら、日本霊異記のこの話を思い出した。
我が子を思うあまり息子のマラを吸う女の話。
女人の大きなる蛇に
婚 せられ、薬の力に頼りて、命を全くすること得し縁 第四十一(前略)
愛欲は一つに
非 ず。経に説きたまへるが如 し。「昔、仏と阿難と、墓の辺 よりして過ぎしに、夫と妻と二人、共に飲食 を備 けて、墓を祠 りて慕 ひ哭 く。夫恋ひ、母啼 き、妻詠 ひ、姨 泣く。仏、妻の哭 くを聞き、音 を出して嘆 く。阿難白 して言はく、『何の因縁を以てか、如来嘆きたまふ』とまうす。仏、阿難に告 りたまはく、『是の女、先世に一 の男子を産む。深く愛心を結び、口に其の子の閇 をすふ。母三年を経て、たちまちに病を得、命終 の時に臨み、子を撫で閇 をすひて、かく言ひき。「我、生々 の世、常に生れて相 はむ」といひて、隣の家の女 に生れ、終 に子の妻と成り、自 が夫の骨を祠 りて、今慕ひ哭く。本末 の事を知るが故に、我哭くらくのみ』とのたまへり」(後略)
要約すると、愛欲の形はいろいろである。それは経典に説かれている通りである。
昔、お釈迦様と弟子の阿難がある墓を通り過ぎるとき、墓の前で悲しんでいる男女がいた。その様子を見て仏は深く嘆いた。不審に思った阿難がそのわけを聞くと仏は語った。
「墓の前で泣いている女は、前世に一人の男の子を産んだ。女はあまりにも深く我が子を愛していて、その子の陰茎を口で吸うほどだった。それから3年してその女は病に倒れ、臨終の間際に子のマラを吸って『私は今後生まれるたびに、常にこの子と行きあうように生まれ、ずっとその妻となろう』と誓って死んだ。
そして隣家の娘として生まれ、その子の妻となり、自分の夫の骨を葬って、今、慕い泣いている。私はそのことを知っているがゆえに哭くのだ」
この話は題名にあるとおり、前半で蛇に犯された女の話が出てくるのだが、この段は全体的にかなり難解で、いくつかある現代語訳の本もすべて違う解釈で訳出されている。実は前述の要約箇所も厳密に訳すといろいろおかしなところが出てくる。
たとえば墓の前にいた男と女だが、女の方は息子のマラをすすり、生まれ変わってその妻となった女であることは間違いない。しかし一緒にいる男は果たして現在の夫なのか、それともかつての夫で今は義父にあたる男なのか。誰を弔っているのかを含め、このあたりでそれぞれ意見が分かれるのだ。
とくに「夫恋ひ、母啼き、妻しのひ、姨泣く(原文では『夫恋母啼 妻詠姨泣』)」をどう解釈するかで変わってくる。
講談社学術文庫では、墓の前で泣いている男は、女からすれば前世の夫であり、現在の義父として解釈されている。
講談社の中田祝夫は「夫は死んだ妻を慕って泣き、妻は、母としては子の死を悼み、また妻として夫を、女として恋人の男を思い出して偲び泣いていた」と訳していた。
つまりその墓は母と息子、つまり今そこで泣いている女の前世の自分と、今は夫であり、前世の息子だった男の墓という解釈になる。
しかし、ちくま学芸文庫の方は墓の前で泣いている男は、女にとって現在の夫であり、かつての自分の息子だとしている。
ちくまの多田一臣はさきほどのところを「夫は母を恋慕って泣き、妻は夫の母を思い起こして泣いているのだった」と訳していて、こちらの場合、弔われている死者は、男にとって父母であり、女にとっては前世の自分とその夫ということになる。
この話自体はどこぞの経典が出典元ということになっているが、そもそもその経典が本当にあるとして、それがインドから渡ってきた経典とはとても考えにくい。
インド人は死んだら死者をガンジス川に流す。
だから阿難の墓も竜樹の墓もない。例外もないわけではないが、一般的に墓を作って供養するってことはまずしないのだ。
盂蘭盆経という中国で作られた偽経があるが、それと同じ類の経典であろう。
それと多田訳にしても中田訳にしても自分が少なからず違和感を感じるのは、おそらくこの妻は前世の記憶など持っていないんじゃないかという点だ。
下手に前世の記憶があるかのように錯覚しているから「母啼き」というのが引っかかってくるのではないだろうか。
この文章を素直に読めば、死んだのは夫の父であり、妻の義父であろう。
最初に「夫と妻と二人」とあるから混乱するが、墓の前ではその二人が飯と水をあげていたということで、その傍らに父の母、つまり夫からすれば祖母もいて啼いた。また伯母のような親戚もいて泣いた。
それでいいのではないか。
その点、東洋文庫の訳は素直で「夫は恋したい、母は泣き、妻は嘆き、伯母は泣いていた。仏は妻が泣くのを聞いて、声を出して嘆いた」(153p)となっていた。
それと「夫は恋ひ」の「恋」の字だが、大乗経典では衆生が仏を「恋慕」するという使い方をよくする。
したがって『夫恋母啼 妻詠姨泣』を伝統的な仏教解釈で読み解くなら、衆生が涅槃した仏(それは自分の仏性とも言える)に対して恋慕している状態とも取れる。
妻は自分が過去世にどういう因縁をもっていたかはよく知らない。わからずに泣いている。
それを知っているのは仏だけだ。
つまりそれだからこそ「(過去世の)夫の骨を祠りて、(そのことを知らずに)今慕ひ哭く」という皮肉を嘆いたのではないか。
いや、待て。
死んだ父親は生前、そのことを知っていたというのはどうであろう。
自分の妻が亡くなる前に言い残した言葉を、傍らにいて聞いていたとしても不思議じゃない。
さらに老母も伯母もそれを聞いていたとしたら。
当事者以外、みなその因縁を知っている。
そうなると泣いている意味も人によって微妙に違ってくる。
素直に悲しめたのは当の夫婦だけってことになる。
愛欲の恐ろしさというのは実はそういうところにあるのかもしれない。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
フェチを追求するってそういうことだからね
- [2009/09/05 11:54]
自分が日本社会について考えるときのベースになっている視点は中根千枝の「タテ社会」3部作と言っていいだろう。
最初の『タテ社会の人間関係』を読んだのは高校1年生の夏だった。
学校の夏休みの課題だったのだが、人とうちとけるのが苦手で基本的に単独行動が好きだった自分にとって、集団で動くことの息苦しさがどこからくるのか、この本を読んでわかった気になった。
| タテ社会の人間関係―単一社会の理論 (講談社現代新書 105) | |
 | 講談社 1967-02-16 売り上げランキング : 19902 おすすめ平均   日本特有のタテ社会を分析した40年前の名著。分析は人類学的、かつ、社会学的。 日本特有のタテ社会を分析した40年前の名著。分析は人類学的、かつ、社会学的。 日本人の仕組みがわかる! 日本人の仕組みがわかる! 気付かされる可笑しい日本人 気付かされる可笑しい日本人Amazonで詳しく見る by G-Tools |
中根さんの考えた「タテ社会の人間関係」というのは基本的に場の力関係のことだ。
日本人は「ウチ」と「ソト」を強く立てわけ、普遍的な価値観より内部の不文律のルールを優先させるところがある。「身内の恥」をさらすことは悪で、たとえそれが非道なことであっても内部は内部で処理しようとする。外に漏らせばそれは「チクった」ということになり、排撃され干されたりする。
「ヨソ(ソト)」から見れば「ウチ」は閉鎖的で、処分も身内に甘いように感じる。
自分の所属する「場」を大事にするということは、「ウチ」に甘く「ソト」には厳しいという構図になる。
ふだん激烈な政治批判をしている人間が、自分の所属する業界や団体のこととなると途端に口をつぐみがちになるのはそういうことだ。
だから「ソト」の問題には「膿を出せ!」とか言っているような人間が、自分の所属する身内の不祥事に関しては、暴露する人間にルール違反だと批判したりするなんてことが起こる。
そこには大きな矛盾があるはずなのだが、当のご本人は意外と気づいてなかったりする。
つまりウチに対しての倫理観とソトに対しての倫理観との間にズレがあるのが当たり前だったりするのだ。
逆にそこをヘタに気づいてしまうと、正義感が強く潔癖性な人は、鬱病になってしまうじゃないかと思ったりする。そういう心の傷を持っている人、結構、廻りにいたりする。
この中根理論を少し違った観点で解説したような本がある。
| 母性社会日本の病理 (講談社プラスアルファ文庫) | |
 | 講談社 1997-09 売り上げランキング : 11322 おすすめ平均   日本社会の精神的構造が少し見えてきました 日本社会の精神的構造が少し見えてきました 現代にもあてはまる日本社会の病理 現代にもあてはまる日本社会の病理 今もって問題作である。 今もって問題作である。Amazonで詳しく見る by G-Tools |
「タテ社会」3部作の掉尾、『タテ社会の力学』にも日本の父親と母親の役割について語られているところがあるが、河合隼雄は『母性社会日本の病理』でタテ社会を「場の倫理」という言葉に置き換え、「場の倫理」=「母性」、「個の倫理」=「父性」と割り振っている。
自分の場合、「母性」「父性」という言葉を最初になんとくなく理解したのは、この河合隼雄を通してだった。
母性とは「包含する」力であり、すべてのものを良きにつけ悪しきにつけ包み込む。
それに対し父性とは「切断する」力であり、ものごとを善と悪、自己と他者、主体と客体などに切り分け峻別する。
心理療法家でもある河合隼雄は、自分の経験したさまざまな臨床例から日本社会は母性の強い社会であるとし、こんな例を上げている。
それは青少年の指導を行っている人にお聞きしたことであるが、シンナーの吸引をしていた少年たちに、その体験を聞いてみると、彼らは一様に観音さまの幻覚を見、その幻覚の中での、何ともいえぬ仲間としての一体感に陶酔していたという。つまり、社会から禁じられているシンナー遊びをする点においては、反社会的、あるいは反体制的ともいえようが、求めている体験の本質は母性への回帰であり、わが国の文化・社会を古くから支えている原理そのものなのである。
河合隼雄『母性社会日本の病理』講談社+アルファ文庫 30p
これに類することは処々に見られ、これらの反体制の試みが簡単に挫折する一因ともなっている。このようなことが生じるのは、結局は日本人がなかなか母性原理から抜けだせず、父性原理に基づく自我を確立し得ていないためと考えられる。
これが書かれたのが1976年なので、ここに出てくる「観音」は今となっては別の形を変えていそうだが、昨今のヱバァ現象やちょっと前のエウレカなどを見るといまだに日本人のグレートマザー回帰は強いんじゃないかと思う。
昔なら「寅さん」なんかそうか。
今日、更新した「僕にだけ優しい千里ママ」を見ながら、母性について考えていた。
日本のエロもまた「母性」が根っこにあるよなぁ、と。
なんだかんだ言って、熟女モノは「母子相姦」が主流を占めているし、そんなに直接的なものでなくても、痴女モノにしても陵辱モノにしても母性との向き合い方の違いだけで、同じ構図になっているんじゃないかと思ったりしている。
河合隼雄の言葉を借りてもう少し母性について説明すると
母性の原理は「包含する」機能によって示される。それはすべてのものを良きにつけ悪しきにつけ包みこんでしまい、そこではすべてのものが絶対的な平等性をもつ。「わが子であるかぎり」すべて平等に可愛いのであり、それは子どもの個性や能力とは関係のないことである。
河合隼雄『母性社会日本の病理』講談社+アルファ文庫 19p
しかしながら、母親は子どもが勝手に母の膝下を離れることを許さない。それは子どもの危険を守るためでもあるし、母――子一体という根本原理の破壊を許さぬためといってもよい。このようなとき、時に動物の母親が実際にすることがあるが、母は子どもを呑みこんでしまうのである。
産み育てる愛に満ちた母親像と、つかんで離さず、死に至らしめる醜い母親像は、ひとりの女性の中に共存している。われわれは普通には、これほどの暗い半面を見ることはなく、温かい、やさしい母の愛のほうを強調して見る。しかしながら、実際には、母子心中の事件や、嫁と姑との争いの中に、あるいは自分の子どもを、自分の思いのままに動かそうとする母親の強烈なエゴイズムの中に、この暗い半面を見ることができるのである。
河合隼雄『母性社会日本の病理』講談社+アルファ文庫 264p
昨日、ついでに友田真希さんの「僕にだけ優しい真希ママ」を見ていたら、みのる監督の作品を思い出した。
前にも書いたことがあるが、ビーパップ・みのる監督の母子相姦モノはどこか壊れてしまった母性という感じがして生理的に落ち着かないときがある。
でも旗監督のを見ながら、この二人の描く母性はまるっきり正反対のようでいて、実はどちらもちゃんと母性を描いているんだって思った。
特に「溺愛ママ」シリーズと「僕にだけ優しいママ」シリーズを見比べてみるとよくわかる。これはコインの裏表だって。
ときどき女性で「自分はファザコンなの」って自ら申告する人がいるが、よく聞くとどうも父性を求めているというより母性を求めているように思うことがある。
あえて言うなら男装の乳房をまさぐりたがっているっていうような。
翔田さんの吸茎を見ながら、「あっ、そういうコは、ひょっとしてちんちんが乳首になっているのかなぁ」なんて思いつつ淫語カウントをしていた。
もちろん竿を握ってね。
淫語魔のおっちゃんはときどきそんなこと考えながらAV見て、それでもやっぱりゴニョゴニョして、次の瞬間、世界を見下ろすような哲学者になったりするんですよ。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(3)
- この記事のURL |
- TOP ▲
でもやっぱりたとえが気に入らねぇーなぁ
- [2009/08/20 22:22]
えっーと明日の更新分の抽出分はすんでいるのだけれど、あいかわらずプログラムのテストにはまって、なかなか進まない。
細かいところでいちいちエラーが出てしまっていたりして、そのたびに立ち往生。
根本的な理解もないまま見切り発車しているからなんだけど、とかにく「まずプログラムを書いて、動かしてみて、エラーを出して、ネットで調べて、直して、また動かして、PCに向かってないときは本で基礎知識を勉強して」ってなことを1ヶ月以上やっている。
ああもっとじっくりことを構える時間がほしいなぁ。
昨日から前に買っておいて読まずにいた『ゼロ年代の想像力』っていうのを今さらながら読み出したんだけど、なんか今のところ、いまひとつ内容的にしっくりこないなぁ。
 | ゼロ年代の想像力 早川書房 2008-07-24 売り上げランキング : 13567 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
前に二村さんが「草食系」でTBSラジオに出ていたのを聞いたとき、なぜこの人たちはマンガやアニメで世相を語っているんだろうと不思議に思ったもんだったが、そのときと同じニオイがする本だ。
あのラジオ、マンガの例自体はわかるんだけど、あれは偏りすぎたよね。
たとえば石坂洋次郎の話をするヤツとか誰もいないんだもん。庄司薫なんて思いっきり草食系男子っぽいし。
あと言っていることがよくわからないってこともあったんだけどね。
東浩紀の主張を、本書の言葉に置き換えながら要約しよう。東は現代の世の中をデータベースと、そこから読み込まれる小さな物語として捉える。かつて――近代においては、(社会全体を説明する)大きな物語の部分集合として(個人が生きる)小さな物語が存在するされー型の世界像が人々に共有されていた。
宇野常寛『ゼロ年代の想像力』早川書房 2008.07.24 36P
しかし、ポストモダン状況の進行に伴って、大きな物語は解体され、世界像は秩序だったツリーから無秩序なデータベースへ移行する。そんなポスモダンの時代、人々は歴史や社会の与える大きな物語ではなく、情報の海としての静的に存在するデータベースから、自分の欲望するとおりの情報を読み込んで「小さな物語」を自身で生成する。そのため、人々は意味の備給にコミュニケーションを必要としなくなる――東はこれを「動物化」と呼んだ。
ここに書いてあるのもさ。今はちょうどデータベースの勉強をしだしたこともあって、この喩えの意味を直感的に理解できるけど、半年前のおっちゃんだとあんまりよくわからなかったろうなぁ。
実は今の悩みはまさにこれで、マニュアルは今のところツリー構造になってるいんだけど、データベース化するにはツリー構造そのものを一回壊さないといけないかなぁなんて考えていたもんで余計切実な話のように思えたよ。
まぁそんな大規模なサイトでもないし、今のままでも十分問題ないんだけどさ。
あと、昨日は借りているサーバー屋さんに「容量がオーバーしてますよ」って、ゴラぁッされてしまいました。
最近、よく質問メールもしているんだけど、素人相手にちゃんと答えてくれてありがたい限りです。
たぶん当分は初心者丸出しの質問メールが届くと思うけど、もうしばらく付き合ってね。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
淫語AV史上まれに見る滑舌のよい淫語コーナーだった
- [2009/08/06 23:11]
今、PHPを使ってページを作り始めたところなんだけど、まだまだ先が長いね。
こんなことならもっと早く着手すべきだった。
いずれにしろこれがうまくいけばかなり更新が楽になる。
データベース的な要素も強くなって、メーカー別やらシリーズ別のページも自動生成されるようになってくれるだろう。
いちいちリンクを貼ったりする作業もなくなるし、デザインもテンプレートみたい自由にカスタマイズできるようになるかもしれない。
どちらにしろもっと勉強しないとなぁ。
最近読み出した本。
 | オオカミ少女はいなかった 心理学の神話をめぐる冒険 新曜社 2008-10-03 売り上げランキング : 74952 おすすめ平均  Amazonで詳しく見る by G-Tools |
この中で「まぼろしのサブリミナル マスメディアが作り出した神話」っていう章がある。
誰もが一度は聞いたことのある実験、ある映画館で1/3000秒だけ「ポップコーンを食べろ」「コカコーラを飲め」という画像を入れたところポップコーンやコーラの売り上げが急激に伸びたという話。
これ、実はアメリカの広告屋が言い出したことで、学者が発表したものではないんだって。
まともな論文ひとつ学会に出されたことはないらしい。すなわちでっち上げだった。
「彼らがやったことは罪深いが、一方で、科学者がそのことを批判せず、実話として語り継がれてゆくのを放置することも、同じだけ罪深いことなのではないか」と著者は訴えているわけだけど、こういうのって一度ひろまってしまうと修正するのになかなか難しいものがあるよね。
血液型占いなんかがそうだもんなぁ。テレビとかの後押しなんかあった日にゃ、もう影響は甚だしい。
実際、自分が「サブリミナル効果」っていうのを知ったのは、「刑事コロンボ」でサブリミナル効果を使ったトリックがあったからで、こんなもん子どもの頃、見ちゃったらまともに信じちゃうわな。
その同じ章のところで、エリオット・マクギニスって学者の興味深い実験が載っていた。
ある単語を被験者に瞬間的に提示して、それがなにかを答えてもらう。最初は提示時間が短すぎてわからない(最初の提示時間は10ミリ秒)。しかし、提示時間を長くしてゆくと(1回の提示につき10ミリ秒長くする)、ある時間からなにが提示されたかわかり始める。これが認知閾に相当する提示時間である。提示された単語は、penisやbicthやwhoreといった口にするのがはばかれるような単語(ここではタブー語と呼んでおく)とmusicやtradeのようなふつうの単語(中性語)である。この認知閾の測定と同時に、被験者の指に電極をつけ、指の皮膚の電気抵抗も測定する。これは、心理学ではGSR(皮膚電気反応)と呼ばれているものだが、これによってそのときの被験者の情動状態(快不快、覚醒、興奮、心の動揺)が測定できる(いわゆる「嘘発見器」と同じものだ)。
鈴木 光太郎『オオカミ少女はいなかった』新曜社 2008.10.3 55p
マクギニスが得た結果は次のようなものだ。タブー語は、中性語に比べ、認知閾が高かった。中性語では認知閾の平均が0.64秒、タブー語では1.20秒だった。つまり、タブー語は、中性語の2倍長い提示時間でないと認知できなかったのだ。
ところが、単語を認知できなかった時、GSRの値は、タブー語の場合は中性語に比べて一貫して高い値を示した。つまり、両者とも認知できていないのだから、GSRは同じになってよいはずだが、そうならずに違いがあった。このことは、タブー語は認知(意識)できていないけれども、情動反応からすれば実は見えていたということになる。
つまり淫語みたいな言葉はふつうの言葉にくらべ、頭ではなかなか認識しにくいが、心や体の方はなぜか頭よりも早く反応してまうってことらしい。
これはこの作者も言っているように、「聞き取ってはいるんだけど、そんなことを言って間違えたら恥ずかしいと躊躇してしまい反応が遅れている」ってこともあるだろう。
いや、むしろだからこそ淫語っていうのは興奮するわけでもあるんだなぁ。
AV見ていて、最初に女の人が淫語を発するときにこの微妙な反応が見えるときがある。
その空気が見たくて最初の淫語発言を楽しみにしているところすらあったりする。
ところがだ。そこで男優が聞き返したりするよね。
聞き返してもう一回言わせたり、羞恥をあおったりするのはいいんだけどさ。
この聞き返し方が悪いと絞め殺したくなるときがあるね。
妙に、はしゃいじゃって言葉を畳みかけたり、わざとらしく声をうわずらせたりして、女性の微妙な反応が男優のテンションで落ち着いて観察できやしない。
かといって「なんでおまえそんなに偉そうなんだよ」って態度で言葉責めするヤツも腹立つしね。
志良玉団子なんて途中まではいいんだけど、ヤツは段取りを考えてさっさと進めちゃうところがあるからダメなんだよねぇ。

一番好きなのは保阪順かなぁ。
とぼけている感じがよくてさ。
すっとぼけながらすぎはら美里に淫語あおりしてみたりね。
「淫語しようよ3」での早坂晃子とのやりとりなんか最高だったよなぁ。
あの掛け合いはおもしろかった。
ああいうのまたやってくんないかなぁ。
「うぶちん」はなんか違うんだなぁ。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
自他皮膜論
- [2009/07/29 23:58]
近松の「虚実皮膜論」の「皮膜」を「ヒニク」とわざわざ仮名をふったりする辞書もあるが、「広辞苑」や小学館の「国語大辞典」は「きょじつひまく」を取っているようだ。
本来、どちらの読みが正しいのかはわからないが、どちらしろ漢字で書き表すなら「皮膜」の方がよく言い得ているように思う。
真実というのは常に皮膜にくるまれている。ふだんは覆われていてその姿はなかなか簡単に見ることができない。
「化けの皮」といった言い方もあるし、人間というのは皮の膜ひとつでようやくその姿をとどめているにすぎないのかもしれない。
そもそも「自分とは何か?」と考えたときに、自分の持つこの「肉体」というのはずいぶんあやふやな境界線でできていることに気がつく。
たとえば今、目の前に松屋のトマトカレーがあったとしよう。
このカレーはいずれ自分の口に入るとはいえ、いったいどの段階で自分の血肉になったと考えればいいのだろう。
舌の上に乗った瞬間だろうか?
胃に入った瞬間?
消化され始めたときだろうか?
「消化」と言ったって、どのあたりからだろう?
消化酵素がとりついた瞬間?
分解しだしてから?
完全に人間の吸収しやすい栄養素になったら自分の血肉になったと言えるだろうか?
それにより体内にできたウンコは自分の体の一部とは言えないのだろうか?
あれは体を通過しただけだからもとから血肉とはなってなかったのか?
それなら尿はどうだろう。
これは体の中で作られた排泄物だ。
いやもっとわからないものがある。
呼吸だ。空気を肺に取り込んで、酸素を吸収し、二酸化炭素を排出する。
この酸素はいつの段階で血肉となるのだろう。逆にはき出された二酸化炭素はどの瞬間から自分の肉体の一部でなくなるのだろう?
そもそも単に人間の肉体は、さまざまな分子を仮に集めて結びつけているだけにすぎない。だから始終、分子レベルで入れ替えを行いつつ存在しているだけとも言えるのだ。
人間の肉体というのは、いくつかの決まり事に則ってエネルギーを入れ替えつつ、常に再構成しているにすぎない。
もっともそれは素粒子レベルでいえばすべての物質にもあてはまることなのだが。
仏教ではこれを「空」という。
仮に集まった肉体を「仮」という。
しかしそれはなにもでたらめに集まっているわけではない。やはりなんらかの法則がある。それを「中」という。
この五体を指して自分という存在があるのではない。
その五体を包む「皮膜」は決して自分と他をはっきりと分かつ境界線とはなりえない。
むしろとりあえず置かれた補助線のようなものにすぎないのかもしれない。
この「自分だと思っている」肉体は、宇宙の塵のひとつとしてつながっている。
「自」は「他」なしで成り立つことない。他もまた自の一部であり、自もまた他の要素を借りて存在しているのである。
これを「縁起観」という。
「虚実皮膜」とは「自他皮膜」のことと言えるのかもしれない。 虚といい、実といってもそれは他人の目を意識して成立する概念であろう。
所詮、人の幸不幸は「他人とのつながり」の中で発生するものだ。
だからこそ「よくできた人間ドラマ」は、それが悲劇であれ喜劇であれ、人をなぐさめる力があるのだ。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲



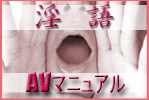
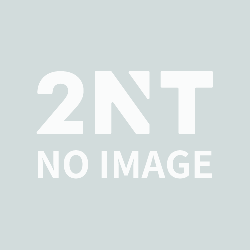
感動した
ありがとう名無し@ボヤキスポンサーサイトがうざいので更新は必ずするつもりです。
今年はようやく淫語魔に戻れるんじゃないかと思っています。淫語魔ものすごく勝手なイメージなんだけどね山下さんの印象は、エロ仙人ですかねー。淫語魔「名前のない女たち」AVレビューどうなっているんですかねー。今度、ナカムラさんに聞いてみます。淫語魔