きっと栗本薫はおしゃべりに違いない
- [2008/10/23 23:01]
しかしグイン・サーガなんだけど、これやたら男の登場人物たちがしゃべりまくる。
なんでこんなにおしゃべりなんだろう。
主人公のグインっていうのは豹頭人身のヤツで、始まったばかりこそやや無口で、感情を表に出さないニヒル野郎だったはずなんだけど、これが途中からしゃべるしゃべる。獣頭なんだから吠えたり唸ったりしとけばいいのにペラペラペラペラ減らず口を叩いたりする。
しかも栗本薫は脳内で思った繰り言まで書いちゃう人だから、一度、何かを考えさせるとこれまたクドクドああでもないこうでもないと言いはじめる。それが2ページ、3ページにわたったりする。
今、10巻目に突入したところなんだけど、ほかの男性キャラもみーんなおしゃべり好きで、高倉健みたいなヤツは出てきそうにない。ずっとこんな調子で進むのかなぁ。
「男は黙ってサッポロビール」だろ。
三船敏郎が昔、そう言ってたぞ。
ところで、このグインつながりでハヤカワ文庫の棚を見ていたら、なんと『クラッシャージョウ』シリーズが置いてあるではないか。今年の秋から改めてハヤカワで刊行されてるんだね。
 | 連帯惑星ピザンの危機 (クラッシャージョウ1) (ハヤカワ文庫 JA タ 1-11 クラッシャージョウ・シリーズ 1) (2008/09/25) 高千穂 遙 商品詳細を見る |
それで今回、初めて知ったんだけど、第1巻はソノラマ文庫の頃になんか改訂版が出ていたらしくて自分が読んだヤツとは結末が違うんだって。こりゃあ買わなぁいかんだろうと思わず買ってしまった。
どうしよう?
このままハヤカワの計略に乗っかっていってしまうのか。
次回は雪見紗弥の雌女ね。
その次は二村作品をやって、そのあと久しぶりに集団モノでもいこうかなぁと。
たぶんそこのメーカーまだマニュアルにUPしたことがないはずなんでちょうどいいかと。
この調子だと土曜日頃かな。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
アルスラーン戦記も別の意味でいつ読み終えられることやら
- [2008/10/06 00:07]
いよいよ今日から『グイン・サーガ』を読み始めた。
いまのところ面白い。
 | 豹頭の仮面―グイン・サーガ(1) (1983/01) 栗本 薫 商品詳細を見る |
ネットでいろいろ見た範囲では6巻からさらに面白くなり、16巻までは間違いなく面白く、40巻ぐらいまではなんとかクオリティがたもたれているが、50巻あたりからだんだん惰性となり、60巻以降はもはやストーリーも薄く、あとは意地になって読みすすめるものらしい。(多分、人によって分岐点になる巻数の違いはあるだろう)
それで前回書いた淫語魔少年が「読むなら物語が完結してから」と思った理由だけど、あとがきを読んだら思い出した。
ちょうどこの作品に興味を持ったとき、第1巻目『豹頭の仮面』の記述の中で、癩病を患ったとされるキャラクターを登場させ、そのことで全国ハンセン氏病患者協議会(全患協)から猛抗議を受けたことがあった。
結果、訂正文をつけることとなり、最終的には一部を書き換える改訂版を出版することで作者なりの決着をつけてみせた。
まさにこの本に興味を持ったときに起こった出来事だったので、淫語魔少年としては出端をくじかれる格好となった。
それで読むなら完結してからにしようと思ったんだった。
まぁ、ほかにも読むものはいくらでもあったしね。
その改訂版のあとがきにこんなことが書いてあった。
「常識」というなんてサベツしないといっといてサベツじゃないか、と云って来た人、キミはジョークというものがわからんのかね。そしてまた差別というのは冗談ごとじゃないのですよ。世の中のことを何でもビックリハウス的に考える、というのは、時として罪なのです。「差別」ということばの重い意味について、半年あまりずしんとうけとめて来た人間にとって、少女マンガを知っているか知らないかでサベツした、などという云い方は冗談ではうけとれませんでした。そして、「差別」をうけている側にとってのいたみはもっと、我々の想像もできぬほど深いのです。できれば皆さんも、これを機会にそうしたことを考えて下さい。そして、自分の文章と小説とに深い誇りと情熱とをもっている人間が(そのためにいつも校正さんと押し問答になる)なぜ、あえて自らの文章を改訂したのか、ということも考えてください。
栗本薫 グイン・サーガ①『豹頭の仮面』ハヤカワ文庫 1983.1.31改訂版 284p
今ひとつ経緯がわからなくて、あとでネットで調べてみようと思うんだけど、いずれにしろ全くもってこちらに非があるにせよ、他人の抗議に押される形で自分の書いたものに手を入れなくてならないことは、作家にとってなんとも情けなく辛いことだったはず。
でも不特定多数の人に自分の書いたものを公開している以上、作家はそれだけの責任を負っているということだ。栗本薫の態度は立派というべきなんだろう。
ところで、問題はいつ読み終わるかなんだよね。
高校生ぐらいの時は1日に1.2冊なんて楽勝だったけど、今はそんなに時間はとれない。できて週3ペースなんじゃないかと。
今月出るらしい新刊を含め123巻を単純に3で割ったとして41週。
これって人間の子どもが受精してから生まれ、なおおつりがくるような長さじゃないか。
まぁとにかく賽は投げられたということで、無事全巻読み終えることができますでしょうか。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
「ゴルゴ13」読破よりも大変なことは間違いないな。
- [2008/09/25 23:05]
ようやくみひろのMVを見終えたので、これからデータの更新分を作るのだ。
更新が遅くなるのは単純に忙しくなっているときか、Web技術の取得に励んでいるときか、何かの本にのめり込んでいるときなんだけど、今回は源氏物語関連の本を読みあさっていたもんでちょいと遅くなってしまった。
 | 源氏物語の時代―一条天皇と后たちのものがたり (朝日選書 820) (朝日選書 820) (2007/04/10) 山本 淳子 商品詳細を見る |
大塚ひかりさんのブログにあったから取り寄せてみたんだけど、すっごく良くできていて面白かった。要は清少納言と紫式部の生きた時代を概観してみせた本なんだけど、このあたりは断片的に理解している程度だったので、この本によっていろんなものがつながってきてかなり見通しが良くなった。
初心者にもわかりやすいので、歴史好きの人、平安貴族に興味を持った人にはオススメ。
この間、とあるSEO対策の会社からリンクの依頼を受けた。
広告と言うよりうちのサイトからの被リンクを買いたいみたいで、その会社のHPを見てもしっかりしてそうだったし、値段の提示までしてきたので乗っかることにした。
今までも出会い系とかワンクリとかからの依頼はあったけれど、ちゃんとしたところからこういう形で依頼されたのは初めてだったので結構うれしかった。
それでもいちおうリンク先を覗いてみた。
どれもアダルトリンクなんだけど、風俗サイトを見ていくうちに「ああこりゃ、雑誌が売れなくなるはずだわ」と思った。
むかしはこの手の情報は風俗雑誌とか買って集めたりしたんだろうけど、今は携帯さえあればタダで「ナイガイ」くらいの情報が手に入る。
そのなかのソープランドの携帯サイトなんだけど、インタビュー記事を見ていたら「好きな本は?」という質問に「120巻ぐらいあるシリーズものなんだけどマニアックだから内緒♥」みたいなことを応えているソープ嬢がいた。
そんな長い巻数を出している小説なんて一つしかない。
「グイン・サーガ」を知ったのは高校生の時だったと思う。
日本のSFに目覚め、眉村卓、小松左京、筒井康隆、光瀬龍、豊田有恒なんかを読んでいるうち、平井和正や高千穂遥、それとこれは少し後だけど新井素子、火浦功の本を読むようになった。『銀英伝』もこの時期にスタートしたんじゃなかったか。
今で言うライトノベルっていうやつなんだろうけど、この頃はまだそんな言い方をしてなくて「Jファンタジー」とか言っていた。
自分はそのうち海外の方に目がいくようになって「ローダンシリーズ」や「エルリック・サーガ」なんかを読み始めた。向こうの方がやはりスケールが大きい。
そんな中、唯一、気になっていたのが『グイン・サーガ』。
もうその頃には結構な巻数になっていて、読むなら相当な覚悟が必要だと思った。
栗本薫は中島梓名義の『文学の輪郭』という硬派な文芸評論を読んだのが最初で、そのあと『キャバレー』は読んだけど、どうもファンタジーというのがピンとこなかった。
それでどうしてそういう結論になったかはもう忘れたけど、読むなら物語が完結してからにしようと思った。
あれから25星霜。
とうとう122巻だ。
ソプ嬢のインタビュー見ていたら無性に読みたくなってきた。
今年の秋は「グイン・サーガ」に挑戦してみるか。
これでますますマニュアルの更新が滞りがちになるかもね。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
新造も禿も若後家も 年に一度の色まつり
- [2008/08/12 23:41]
なんだかんだ言って、オリンピックは見てしまうね。
やっぱりスポーツは面白いなぁ。
金メダルとかとられちゃうと何度もリフレインして見たくなっちゃう。
まぁそうやってテレビを見ながら、どうにかこうにか明日の更新分ができた。
 | 消費社会から格差社会へ―中流団塊と下流ジュニアの未来 (2007/04) 三浦 展上野 千鶴子 商品詳細を見る |
この間まで『消費社会から格差社会へ』を読んでいたんだけど、こういうのを読んだあと宮本常一の本を読むとなんか中和されていい感じになる。
現代の問題を現代の視点だけで考えてると、とんでもない事態が起こっているように思うんだけど、その「とんでもない」と思わせるような「常識」も昔からあったわけじゃなくて、つい最近出来た価値観だったりする。
たとえば夜這いの話。
- 大宅
- あなたの郷里の大島あたり、いまでも"夜這い"はあるんですか。
- 宮本
- もうないですね。だってこのごろは電灯がついているから、あれは電灯がなくて暗かったからできたんで……。
- 大宅
- 山陰地方だったか、"夜這いをやめてオートバイ"って青年運動がはじまったとか(笑)。
- 宮本
- 夜這いというのは非常にほがらかないいものですよ。あなたの行った姫島はまだあるといってもいい。あそこの夜這いは娘のところへ行くのでも、そォーッと開けるんじゃない。必ずあいさつして「ごめん」ってはいる。冬なんか拍子木たたいて火の用心して歩くと、寒かろうと寝床であたためてくれるっちゅうんですね。おもしろいのは、あそこにはいまでもクラブが残っていて、タタミ十二畳ぐらいのフトンがある。
- 大宅
- 一枚で……?
- 宮本
- 一枚。それに若い衆がみんなクサビ打つように頭だけ出して寝るんですね。これはハダカで寝るのがいちばんあったかい。あれくらい、みんなが仲良うしとりゃァ、男も女もないですわね。
- 大宅
- そういうこと、教えておいてくれれば、あの島に行ったときに……(笑)。
- 宮本
- あそこの娘さんたちのほがらかな積極性というものは、青年との間にいざこざはないし、実に大っぴらにお互いがつき合えるからでしょう。
- (中略)
- 大宅
- 結婚したあと大丈夫ですか。
- 宮本
- ちゃんと亭主を守る。子どものころ、近くの娘が結婚するとき、もう誰とも関係しないシルシに、以前、関係した男に足袋をくばる。それは紺の足袋にきまっている。「こんのたび限り」(笑)。それを二十七足くばった女があったが、そんなのに限って、世帯持ちがいい。
- 大宅
- 熟練工なんだな。
- 宮本
- 熟練工になって、これがいいってことになると、思い残すことはない。
- 大宅
- そういうのがいい亭主を選ぶ。
- 宮本
- こういう問題がやかましくなったときに、佐賀県で娘たちが「これからどうして自分の亭主になる男をえらんだらいいんでしょう」といったという話があるんですね。一種の試験結婚だから、問題だろうけれど、これっていうのたしかめるのには、それ以外に方法はない。そして、いいのが当たりゃいいでしょう。
対談者は大宅壮一で、初出は「"夜這い"こそ最高の結婚教育」(『週刊文春』68.9.30)、今からちょうど40年前の対談だ。
これを読む限りでは、この頃まだ日本に夜這いの名残りがあったということになる。
 | 日本人を考える (2006/03/16) 宮本 常一 商品詳細を見る |
日本が総中流化したのは高度経済成長期で、それまではフレキシブルながら階層社会はあった。日本の恋愛観・結婚観が固定化されていったのは、ちょうどこの対談があった時期からだったのではないか。
- 大宅
- 学生時代、京都では愛宕祭といって、その日は乱交自由の日……。
- 宮本
- もとは日本各地にずいぶんあったですよ。必ず繁みの中に入ってしなきゃならん。だから、高知の大田口では柴折り薬師という薬師さんがある。柴を折ってするから……。(笑)。
- 大宅
- 東京でもむかし、井之頭公園あたり、ススキの原で、朝行ってみるとススキが倒れている……。(笑)。
- 宮本
- それにもちゃんとわけがあったんです。とくにイネでもムギでも、みのるころにそばですると、みのりがよくなる、というんです。
大宅壮一は1900年のうまれだから、彼の学生時代というと大正10年前後になる。
その頃ならまだ日本中に色町はあったし、こういう色祭りも全国的にいくつかあったのだろう。
もっとも井の頭は「東京」というより国木田独歩が小説に書いた「武蔵野」だ。江戸の町文化とは少し系統が違う。
その武蔵の国府・府中には闇祭りという色祭りがあって、かつては「乱交自由の日」とされていた。
いまならとても考えられないことだろうが。
「最近の女は羞じらいがない」というヤツがいる。
確かに昔の「上流」の「お嬢さん」には羞じらいがあっただろう。でも世の中、みんな原節子みたいだったわけではない。
日本女性が「清楚だった」というのはかなりすり込まれた感覚で、むしろきわめて個人的な好みの問題だと思う。
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
淫語おやじは会話文を重視する
- [2008/07/20 12:51]
連休というのはゆっくりできるようで意外とできない。
さっきまで次回のを必死コいて淫語カウントしていたがタイムアウト。
そろそろ出かけなきゃいけない時間だ。
次のヤツは3時間近くあるもんだから、いつもよりも時間がかかるのだ。
上半期は月2回ってことが多かったから、しばらくは旧作のアップも増える。
それと「エロスの宇宙」以来、ムーディーズ不買期間に入っていたんだが、もう半年経ったことだし、そろそろまた買っていくつもり。まずは中古品で。マニュアルにもそのうちUPしていくかもしれない。
ディープスも実は「淫語」と冠してるタイトルなのに言ってないことがある。そのたびにキレるんだが、どうもここはレーベルによって違いがあるみたいだ。ちょっと今、地雷の避け方を学んでいるところ。
今、ある歴史ミステリー小説を読んでいるのだが、どうも会話文が気になる。
小説で会話文の扱いが稚拙だと読む気がそがれる。とくにそれが怪奇ものとなると自分は少し辛い。
会話文がうまいかうまくないかはいい小説家かどうかの試金石だと思う。
最悪なのはすべての登場人物が同じ口調やリズムだったりすることだ。
これがマンガならゆるせる。たとえばギャンブル漫画の福本伸行のように。
彼の作品は「アカギ」も「賭博黙示録カイジ」もほぼ体言止めで進行。
言い切る感じが、死線を見つめる男たちにとっては有効の会話文。
倒置法の使い方も秀逸。
まさにこれはギャンブルの空気をあらわす福本ならではの会話。
だけどさぁ、これを小説でやられるとどうも気になる。
結局、どの人格もその作家の口調で書いているわけで、そうやって脳の中の繰り言を書かれると、この人には絶対他者がいないんだなぁと思ってしまう。
その土地の方言、職業柄の言い回し、専門用語への目配り、男と女、あるいは子どもの話し方、そういったものの書き分けには不断の観察眼が必要だ。
世間的に名の知れた作家でも下手なヤツはいる。
でもそれを身につけないと、人物に厚みを持たせることができない。
もともと自分はヘミングウェイみたいな観察力に裏打ちされた文章が好きってこともあるかもしれない。彼は外観の描写も素晴らしいが、会話文も実に見事だ。
ヘミングウェイが作家として生きていくことを決めた若かりし頃、パリでの耐乏生活の中、次の言葉を自分に言い聞かせて書いていた。
All you have to do is write one true sentence. Write the truest setence that you know.
(しなきゃならんことはただ一つの本当の文章を書くことだ。おまえが知っているもっとも真実に近い文章を書くのだ。)『移動祝祭日』
- 淫語魔の読書風景 |
- トラックバック(0) |
- コメント(0)
- この記事のURL |
- TOP ▲
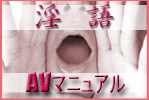
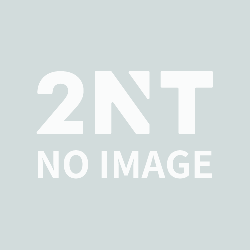
感動した
ありがとう名無し@ボヤキスポンサーサイトがうざいので更新は必ずするつもりです。
今年はようやく淫語魔に戻れるんじゃないかと思っています。淫語魔ものすごく勝手なイメージなんだけどね山下さんの印象は、エロ仙人ですかねー。淫語魔「名前のない女たち」AVレビューどうなっているんですかねー。今度、ナカムラさんに聞いてみます。淫語魔